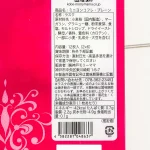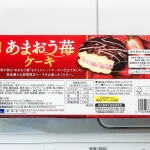11 月は給油一回のみ。燃費は、まぁまぁかな? 暖房も使っただろうし。
遠出という遠出も特になし。ただ埼玉北部や佐野には何度か足を運んでいる。
| 車種:トヨタ エスティマ ハイブリッド アエラス(AHR20W – 公称 18km/L・レギュラー) | ||||||
| Date | 走行距離 | 給油量 | 単価 | 燃費 | メーカー | 給油地 |
| 11/21 | 698.3km | 52.04L | 166-9 円/L | 13.419km/L | ENEOS | 東京都杉並区井草 |
ガソリン代は 157 円 /L と先月に較べると一応安くなっている。そもそも -9 円引きってなんだ?(汗
これは ENEOS のアプリのクーポンなんだけど、この井草の ENEOS はこの値引き幅の変動がすごい。-3 ~ -9 の間で揺れるのだがその根拠がよくわからん。先月も -8 円割引の日があった。ただちゃんと観察はしてないのだが、この井草店、素の値段を高めに設定していてクープンを持ってる人は安く買えるという戦略のように見える。
ファイル名にスラッシュを使いたいとき、全角の/を使ってたんだけど、UNICODE に半角っぽいスラッシュあった。
⧸
これでちゃんとWindowsでファイル名、変更できた。全角だと間延びしてイヤだったのよね。でもコレを使って何か問題が起きないか心配ではあるw#Unicode #29F8
— 宇奈月けやき (@UNADUKI_Keyaki) November 29, 2024
Windows のファイル名で困っている文字がある。それは「/」と「?」と「\」だ。開発ではこれらの文字は避ける習慣が出来ており、困る事はそんなにない。ボクがこれらの文字で一番困っているのが曲名だ。CD からリッピングした際、曲名に / や ? が入っていると保存する事が出来ないので全角の「/」や「?」に変換して保存しているのだが、これがまー間抜けなのだ。日本語の曲名ならそんなに違和感はないんだけど、アルファベットの曲名だと / や ? が妙にでかくてバランスが悪い(汗
で発見したのが↑のツイートというわけだ。実は二種類あって、以下の二つ。
| ⧸ | 29F8 |
| ⁄ | 2044 |
最初の方はちょっと長すぎるかも(汗)。二つ目はちょうどイイ感じ。
どちらもファイル名として保存可能だ。
ただコレを使って全く問題がないのかどうかは、実はまだよく分からない。今の所、音楽プレイヤーで認識しなかったり、URL にしてダウンロード出来なかったりとかそういうことは起きていないが、果たして……。